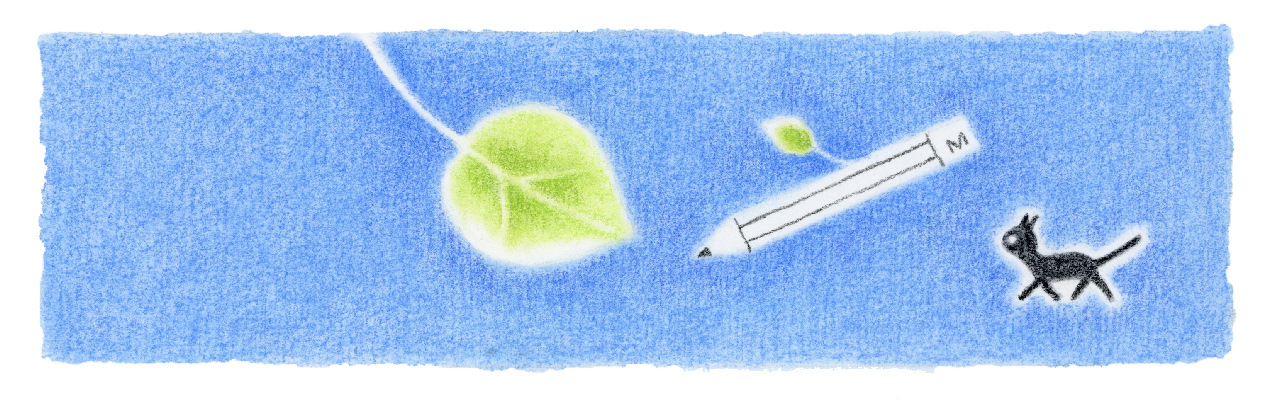
皆さま、こんにちは。
5か月ぶりのミール風ブックトーク「読んでミール?」をお届けします。今回は五感につながる「一文字」テーマシリーズの最終回!「音」「色」「味」「香」に続き「触れる」がテーマです。読書の秋、いつもとは違う視点で本を選んでみるきっかけになったら、うれしく思います。今回も、ブックトーカーふたりのこころの本棚から3冊ずつ、ご紹介します。
第14回「読んでミール?」の始まり、はじまり。
Book Talker Naomi***
1 宮尾登美子 著
『蔵』(1993)毎日新聞社・中公文庫・角川文庫
「触れる」を考えた時、1番初めに思い浮かんだのが「蔵」の女性主人公、烈の事でした。
烈は網膜色素変性症で視力を失い、耳から聞こえる音と手で触る感覚だけで色々な事を判断していくようになります。
蔵人の涼太を意識したのも、心に響く彼の酒造り唄の声と烈を安全な所へ導く時に握った彼の優しい手の温もりです。
烈には、涼太の優しさ誠実さが触れるだけで伝わってきたのだと思います。
将来視力が失われる事を小さい頃から知らされているというのはとても辛い事だと思いますが…迷い悩みながらも覚悟を決めていくその過程が、烈を強い女性に育てたのかもしれません。
一途な烈の生き方には勇気をもらえると思います。
2 窪 美澄 著
『夜に星を放つ』から
「真珠星スピカ」(2022)文藝春秋
この作品は先日の167回直木賞を受賞した「夜に星を放つ」の短編の中のひとつで交通事故で亡くなった母親の幽霊と暮らす娘の話です。
この母親の幽霊にはいくつかの約束事があります。幽霊となった身体は透けていて触れられません。夜も昼も出てこられますが、太陽の光を浴びると一層薄く透けて見えます。声が出せないので全て身振りで表現します。そして何故かその姿は、娘であるみちるにしか見えません。
慣れない料理をする娘を心配そうに見守ったり、お父さんの寝癖を指差して笑ったり…幽霊にしてはとても愛すべきキャラなのは元々のお母さんの性格なのでしょう。
始めは中学校のクラスでいじめられているみちるの妄想かと思いましたが、みちるがイジメの主犯格の子との「コックリさん(注1)」を強制された時、助けに入ったと思われる母親の示した文字に母としての精一杯の思いが伝わってきて涙が滲みました。
最後に眠れないみちるの頭を母親が撫でた時「手の感触は無い。けれど、母さんの手の温もりをかすかに感じた気がした。」の一文にやはり幽霊の母はいるのだと確信しました。
(注1) 西洋の「テーブル・ターニング(Table-turning)に起源を持つ占いの一種、日本では通常、狐の霊を呼び出す行為(降霊術)と信じられており、そのため「狐狗狸さん」の字が当てられることがある。
3 保坂 和志 作
小沢 さかえ 画
『チャーちゃん』(2015)福音館書店
これは芥川賞作家である保坂和志さんが初めて作った絵本です。保坂さんは書いた小説の中には必ず猫が出てくるくらいの愛猫家で、自分の最近亡くなった猫を語り手に死後の世界を描いています。
猫を知り尽くしている作者の紡ぐ言葉は本当に猫が話している様です。
色彩豊かな優しいタッチの絵の中で自由奔放に走り踊る猫の姿には思わず笑顔になります。
実は私も大の猫好きで自宅には現在3匹の猫がいます。以前初めて飼った猫を亡くした時は本当に辛くて悲しくて色々な後悔もしたのですが、この本を読んだ時、姿も見えず声も聞けず触る事さえ出来なくても…こんなに楽しそうにしているのなら嬉しいなと思いました。
そして楽しそうなのは猫だけではありません。犬も亀も蛇も踊り、鳥は歌い、魚は泳いで跳ねています。
色々な生き物を愛する全ての皆様に是非読んでほしいと思いました。
そして最近最愛のペットを亡くしたあなたにも…。
Book Talker Chie***
1 宇山 佳祐 著
『今夜、ロマンス劇場で』(2017)集英社文庫
「触れる」とは何か?と考えを巡らせてみますと、ボディタッチもあれば心の触れ合いもあると気付きます。心の満足やときめきはどちらにも感じることですが、どちらの「触れる」も叶ったとき、やはり人はもっとも安堵するのではないでしょうか。
そんなことを思わずにはいられないのがこの作品で、主人公は映画監督を夢見る青年と銀幕から抜け出してきたモノクロームの世界のお姫様。何しろこのお姫様がやんちゃなのです。そして見事に可愛い。
お察しのとおり、異世界に生きてきた二人が恋をしたら、「触れる・触れない」の問題が出てきます。その境目の切なさに揺れ動きながら生きていく二人の恋物語は、元々は映画「今夜、ロマンス劇場で」で表現されていたもので、本作は映画のノベライズ本です。
ちなみに映画の主演は、綾瀬はるかさんと坂口健太郎さん。はるかさんはさながら「ローマの休日」のオードリー・ヘップバーンのような美しさ。坂口さん演じる青年が老年になり回想しながらストーリーが進むという展開ですが、老年の役を演じたのが加藤剛さんで、この出演作が遺作となりました。映画も小説もピュアな喜びを思い出す秀作です。ぜひどちらも楽しんみてください。
2 石黒由紀子著
『猫は、うれしかったことしか覚えていない』(2017)幻冬舎
猫好きは世の中に山ほどいて、猫好きが読むといい本の広がりも海ほどある。そんな言葉は今思いついたいい加減なことですが、本当に猫が出てくる本(略して猫本)は多いですね。
Nさんに続き、私からも「猫本」をおすすめします。この作品は、猫と暮らしている人はもちろん、猫ともう一度暮らしたい、かつての猫との暮らしを当の猫はどう思っていたのか聞きたい・・・そんなことを思う(私みたいな)人もぜひ読んでみてください。今はもう触れることができなくても、かつて触れていた(触れまくっていた)子を思うとき、このやさしくて楽しい本を読むと心がぽわーんとやわらぎます。
愛猫をなくして今はつらいばかりの人も、時間を重ねるときっと心がやわらぐ日がきます。この本のタイトルだけでも救いですよね。短いエッセイ風の文章ですので、どこから読んでも楽しめます。ミロコマチコさんの絵もとっても味があり、そうそう、ウフフと笑ってしまいますよ。
3 トーベ・ヤンソン+ラルス・ヤンソン著
ムーミンコミックス第1巻『黄金のしっぽ』ほか全14巻(2000)筑摩書房
ムーミン好きの人は、まずはムーミンたちのビジュアル的な愛らしさにはまりながら、じわじわとムーミンたちの暮らしや考えや好き嫌いにも触れて、新たな発見をする人が多いのではないでしょうか。じつは、私もムーミン好き。ムーミンたちの可愛い絵柄を用いたグッズやラインのスタンプなどムーミンものは数々あり、どれも欲しくなってしまうのですが、ある時から、どうしてこんなにバリエーションがあるのか、なぜこんなにも登場人物が多いんだろうと不思議に思っていました。
そんな私が巡り合ったのが数年前に名古屋市博物館で開催された「ムーミン・コミックス展」です。会場に並ぶ原画の数々に驚き、合点がいきました。そうか、そうなんだ!ムーミンは漫画としてもこんなにも豊かに展開していたんだ、と。沸くようにでてくるムーミンたちの表情、しぐさ、言葉。ストーリーも奇想天外だったり、風刺がきいていたり、ミィならともかくムーミンママまでもが意外とストレートな物言いだったりとなんだか大変です。
というわけで、ムーミン好きなら「触れる」といいものとして、ムーミンコミックスをおすすめします。これを読んだり眺めたりしていますと、数多あるムーミングッズの絵柄の「在処(ありか)」に触れることもできますよ。今から20年以上前、筑摩書房から配本されたシリーズを、私も古本で一冊ずつ集めています。
(スタッフN & C)
写真はフィンランドの切手付き封筒。ムーミンの読書がテーマです(笑)

皆さま、こんにちは。
今日は久しぶりにミール風ブックトーク「読んでミール?」をお届けします。今回は五感につながる「一文字」テーマシリーズの3回目!「音」「色」「味」につづき、「香」をテーマにお届けします。風薫る季節、どんな本が並ぶでしょうか。
今回も、ブックトーカーふたりのこころの本棚から3冊ずつ、ご紹介します。
第13回「読んでミール?」の始まり、はじまり。
Book Talker Naomi***
1 中川 李枝子 作
大村 百合子 絵
『ぐりとぐら』(1963)福音館
誰もが知っている「ぐりとぐら」。
森の中で大きな卵を見つけたぐりとぐらが作った食べ物は何でしょう?
その美味しそうな匂いに惹きつけられて森の中の動物たちも集まってきます。
大きなフライパンで作るのでホットケーキと間違いやすいのですが…実はカステラです。
その作り方を試してみたのが青山美智子著「お探し物は図書室まで」に出て来る婦人服販売員の朋香。誰もが知っている「ぐりとぐら」でも覚えている箇所は人それぞれで不思議です。楽しいブックトークの中で人と人が繋がっていく…これもまた素敵なお話です。
(参考)青山美智子 著
『お探し物は図書室まで』(2020)ポプラ社
2 伊吹 有喜 著
『犬がいた季節』(2020)双葉社
犬のコーシローは高校の犬です。
昭和63年に自分を高校で飼う為に頑張ってくれた初代コーシロー会の生徒達を始め、時代を移しながら様々な生徒達の青春を見つめてきました。
ところどころでコーシロー目線の文章が差し込まれるのですが、その中で「匂い」が重要なポイントになっています。
花の匂いやパンの匂い、そして恋の匂いまでもコーシローは嗅ぎ分けられます。
そして最終話にはそれまでの5つの話に登場してきた人たちのその後も描かれていて…きっとコーシローも喜んでいることでしょう。
3 宮尾登美子 著
『伽羅の香』(1987)中公文庫
*香道(こうどう)とは
日本の芸道の一つで香木を焚いて出た立ち上がる香りを賞翫(しょうがん/そのものの良さを味わうこと)し、さらに礼式や作法を加えたもの。
このお話は香道に魅せられた葵という女性のお話です。
素人にはなかなか難しそうな世界ですが、葵は八つで初めて聞いたお香の香りから、かぐや姫を連想する等、香りに対する感性が飛び抜けて優れていて、「香道」の素養を生まれながらに持っていたと言って良いくらいでした。
裕福な山林王の一人娘として育ちましたが、夫や両親を相次いて亡くし、更に子供にまでも先立たれた後、唯一の生きる希望である香道復興の為に莫大な財産を投げ打って尽くします。
しかし思わぬ裏切りにあい身も心もボロボロになった時、再び生きる力となったのもまたお香の香りでした。
他の人が真似出来ない「香と共に生きる人生」を自ら選んで突き進んだ葵。
こういう人がいたからこそ、脈々と文化が受け継がれていくのかと思います。
私も今度「香道」なるものを体験してみたいです。かぐや姫を感じる事が出来るでしょうか?
Book Talker Chie***
1 千葉治子・飯田智子 著
『素敵にアロマテラピー』(2012)保健同人社
心身に不調を感じる親しい人へ、ほんのわずかでも安らぎを感じてもらえないだろうか、とつくづく考えた時期がありました。そして、ふっとたどりついたのがアロマテラピーでした。アロマオイルの香りとその組み合わせの不思議に引き込まれながら、さまざまな本を読み漁り、化学実験のごとく日々ブレンドを試み、せっせと友人たちに渡しました。そんなある日、友人から乳がんになったと告げられました。ああ、私にできることは?と思いを巡らせたときに、また辿り着いたのがアロマテラピーです。
しかし、ホルモンへの作用もあるアロマを乳がんの罹患者に用いても大丈夫だろうか?と立ち止まり、大きなためらいに変わりました。そこに手を差し伸べてくれたのが本書です。本の副題は「乳がんの人の心と体に」。著者のお二人は乳がんを体験されたかたです。お二人が、考え抜いて言葉や写真を選ばれたことを感じます。目には見えないやさしい香りのしおりが挟まれているような気持ちに何度もなりました。
残念ながら本の編集作業中に著者のお一人は亡くなりましたが、きちんとカタチとなり、迷える人の手に届いたのはありがたいことです。今は私の手元にあるけれど、必要な方にそっとお渡ししたくなる本です。
2 阿刀田高 著
『瓶詰の恋』(1984)講談社文庫
短編の名手、阿刀田高さんの作品を読むと、いつもふわりとどこかの国に行ってくるような感覚に陥ります。束の間の脳内旅行の最中、小説に登場するおしゃれな小道具が気になったりするのですが、「瓶詰の恋」に出てくるのは香水瓶。一夜をともにした美しい女性が残していったノワール・ノワールという香り。それは彼女とのめくるめく濃厚な時間を蘇らせてくれるものとなり、惜しみながら瓶の蓋を開け、その香りを嗅ぐ日々の果てに起きたことは・・・。
結末を知っていても、また思い出して読みたくなるのは、窮屈な日々から抜け出して、ふわりと心を浮かせて異世界を味わいたくなるからかもしれません。叶わないことは多くても、夢見ることは捨てなくていい、というふうにも、今なら読み解きたくなります。
3 サラ・B・フッド 著
『ジャム、ゼリー、マーマレードの歴史』(2022)原書房
原書房の「食」の図書館シリーズはどのテーマも興味深く、身近な食べ物を深堀りしていて、世界に広まった歴史、経済的な観点など勉強になることばかり。本書『ジャム、ゼリー、マーマレードの歴史』も大変面白く、旧石器時代後期まで遡るジャムの起源から始まり、16世紀から20世紀までの1世紀ごとのドラマチックな変遷を丁寧にたどっています。
ジャムとは果物と砂糖があればできるもの。果物が持つペクチンという成分と糖と酸の絶妙なバランスによって美味しくなるわけですが、出発点はみずみずしい果物を旬でない時期にも食べるための工夫。オレンジ、ブルーベリー、桃・・・と、それぞれの果物が持つ香りを秘めたジャムをひとさじすくう時は幸せです。ちなみに預言者として知られるノストラダムスは料理研究家でもあったらしく、レシピ付きのジャムに関する書も残しています。ノストラダムスがジャムおじさんだったとは知りませんでした。(ミール関係者にもジャムおじさんがいて、季節ごとにおいしいジャムを作ってくれます!!)
ところで、私がこの本を読んで初めて知ったことの一つに、19世紀末ごろからカナダでは農家のご婦人たちが余った果実などでジャム作りに取り組み、その活動がアメリカやイギリスにも広がり、地域や国を超えて苦しむ人や子どもたちにジャムを送ったということ。戦時中、カナダでは「イギリスにジャムを」という婦人会と赤十字の取り組みが国家プロジェクトにまで展開。国がボランティアに対し優先的に砂糖を配分したそうです。
色鮮やかで栄養満点なジャム。蓋を開けたときにふわりと感じる香りは幸福そのもの。平和な食卓を思い浮かべる人が多かったのではないでしょうか。
(スタッフN&C)
皆さま、こんにちは。
今日はミール風ブックトーク「読んでミール?」の第12回をお届けします。五感につながる「一文字」テーマシリーズの3回目!「音」「色」につづき、今回は「味」をテーマお届けします。食欲の秋であり、読書の秋でもあり。どちらも満たす「味」なひとときにつながればうれしく思います。
今回も、ブックトーカーふたりのこころの本棚から3冊ずつ、ご紹介します。
第12回「読んでミール?」の始まり、はじまり。
Book Talker Naomi***
1 はしもと みつお 画
大石 けんいち 作 (1巻)
鍋島 雅治 作 (2〜21巻)
九和 かずと 作 (21~42巻)
『築地魚河岸三代目』(2000年~2015 年)全42巻 小学館
この作品は「ビックコミック」という青年漫画誌に連載されていたものをコミックス(単行本)にしたものです。
また2008年には映画にもなっています。
元銀行員という素人でありながら妻の実家である築地の魚河岸の世界に飛び込んた主人公が三代目として認められるまでを描いています。
先ずこの主人公の赤木旬太郎は無類の食いしん坊でおまけにどんな繊細な味も感じられるスゴイ舌を持っています。
そして美味しい物を食べる為にはどんな努力もいとわす、知識を得るためには日本中どこへでも飛んでいく行動力もあります。
この本の中ではその回ごとにさまざまなな魚を扱っていて、その生態や特徴、扱い方や料理法などが詳しく載っていますので、魚好きの方は必見です。
食欲がそそられる事間違いなしです。
2 加藤 シゲアキ 著
『オルタネート』(2020年)新潮社
.
第42回 吉川英治文学新人賞受賞
第164回 直木賞候補
2021年 本屋大賞第8位
第8回 高校生直木賞受賞
作者は現役アイドルでこれまで何冊か書いて話題になっていましたが、始めは若い人向けの話だろうと実はあまり期待していませんでした。
でも「オルタネート」と呼ばれる高校生限定のマッチングアプリという設定は古い世代にも分かりやすく書かれていて、何より登場する若い人達の一生懸命な姿にとても共感をおぼえました。
そしてこの本の中で重要な要素をしめるのが「ワンポーション」という高校生の料理コンテストです。
ずっと昔にテレビで「料理の鉄人」というのがありましたが、それと同じように決められた食材を使って時間内にどんな料理を作るかで勝敗が決まります。
始めの書類選考と予選は食材とテーマが先に発表されているので、前もって考えたり研究する時間がありますが、本選に入るとその場での食材・テーマの発表で、制限時間の中で考え作り上げなければなりません。そこでモノを言うのが、これまで培ってきた知識や技術。そして味の記憶です。
主人公も子供の頃の記憶を元に料理を作り出します。
さあ結果はどうなるでしょう?
3 小川 糸 著
『ライオンのおやつ』(2019年)ポプラ社
2020年 本屋大賞第2位
2021年6月ドラマ放映(NHK)
この作品は美しい海にかこまれた瀬戸内の島にあるホスピスのお話です。
「ライオンの家」と呼ばれるその施設では余命宣告を受けた人たちが最期の時を穏やかに過ごしています。
そこでは変化に富んだ朝食のおかゆなど、毎日が楽しみになる身体に優しく美味しい食事が登場します。
そして最大のお楽しみは毎週日曜日におこなう「入居者がもう一度食べたい思い出のおやつの時間」です。
美味しい記憶というのはやはり幸せな記憶とセットになっていると思います。
たとえ高価なものではなくても「大好きな人と楽しく食べた」とか「大切な人の為に心を込めて作った」というエッセンスで例えようもないくらい美味しいおやつになるのではないかと思います。
主人公の30代の女性雫(しずく)をはじめ、小学生の女の子、元喫茶店のマスター、元有名作詞家、少し痴呆気味のシスターなど年齢も経験も様々な人たちが、一緒におやつを味わいながら、その人の思い出を共有し、その人の人生を一緒に振り返るそれは本当に素敵な時間です。
あなたが人生の最期に食べたいおやつは何ですか?
Book Talker Chie***
1 平松洋子 著
『ひとりひとりの味』(2007)理論社
グルメではなくても「味」がテーマとなると、とても悩ましく、親しみと憧れが混じり合うこのテーマは深い!とつくづく思った次第。ということで、まず1冊目は食べ物のエッセイが本当に楽しい平松洋子さんの作品から。
この本は、味覚の勝負は15歳から!と帯のキャッチコピーにもあるように、若い人向けに書かれています。けれどもどこを読んでも、大人ならきっと誰しも、うんうん、そうそう、その通り!と唸ることばかり。例えば、この一文はどうでしょう!「これまた昭和のころ、内田百間(ひゃっけん)というたいそう食いしん坊の作家がいました。ガンコで有名なそのおじいさん作家は、つねづねこんなふうに書いていました。『おなかが空いているのは私のいちばん好きな状態である』 それはどうしてかというと、空腹に耐えながら、ひたすら晩ごはんを楽しみにする。そうするとこのうえない幸福に浸れるのですって。すごい。さすがガンコ者。あっぱれな食い意地です!」百間先生にも当然若い日はあったはずですが、おじいちゃん作家と位置付けるその明るさ。たしかに気骨ある食いしん坊の老作家、内田百間先生の本まで読みたくなる味わいが、平松さんの名文には潜んでいます(笑)。
またエピソードもぎっしりで楽しく、例えば、よそんちのお味噌汁を、理由はないけど飲めないという小学生の話も面白い。「おめえよう、幼稚園児かよ。味噌汁ぐらいで甘えてんじゃねえぞ」とからかう同級生に対して、クールな学級委員長がこういいます。「ほっとけよ。こいつだって、ほんとにハラ減ったら贅沢言ってられねえから」。これは百間先生と同様というより同等、堂々の本筋でしょう。
この本は、味の世界の広さ、深さ、可笑しさのあれこれを、身近だった風景とともに伝えつつ、日々、好きな味にどんなに魅了されているかを私たちに教えてくれます。ちなみに著者の平松さんは幼少の頃から台所が大好きで、ある夏休み、台所に勉強机を移動させてず〜っと居座ったそう。音、匂い、たたずまい、もっとも釘付けになるのはお母さんの仕事ぶり・・台所のすべてが好きな人の文章はおいしいものへの愛でいっぱい。その愛は無限でやさしい、と思います。
2 銀座千疋屋 監修
『くらしのくだもの12か月』(2014)朝日新聞出版
何回も買っているのに、なぜか手元に残らない本というのはありませんか?ふと思いついて、自分の書棚からプレゼントしたくなる・・・そんな本の一冊が、私の場合、「くらしのくだもの12か月」です。果物の名店、銀座千疋屋監修の本ですから、フルーツのウンチクたっぷりで果物写真の美しさにもうっとり。さらに素敵なのは、いちごや枇杷、文旦といった瑞々しい色とやさしい形の果実が表現されている写真に、味わいの余韻が広がるような俳句を月ごとに呼応させていること。綺麗な果実の一つひとつを、写真と言葉の両方で堪能できるのです。
食べたことのあるありふれた果物も、切り取る視線が違えば新鮮に感じられ、その果汁や食感の記憶を辿り直しては、次の季節は必ず味わいたいと楽しみがふくらみます。金子兜太さん、鷹羽狩行さん、中村草田男さん、長谷川櫂さん、稲畑汀子さんら著名な俳人の作が並び、17音に包まれ、そして開かれた光景や思いは、いかにもふくよかです。
林檎のおいしくなる季節、11月の句をご紹介しましょう。「林檎の木ゆさぶりやまず逢いたきとき/寺山修司」コロナの収束まで、逢える・逢えないの心の揺れも、林檎の酸味と甘味がやわらげてくれるといいですね。
ちなみに、この本。私は、食が細くなっておられる方へのお見舞いにお持ちしたこともあります。何を持っていったらその方の慰めや励ましになるのかしらと悩む時の贈り物として、頭のかたすみにそっと置いておくと良い本のような気がします。
3 川勝里美・吉本直子編
『シネマ厨房の鍵貸します』(1996)映像文化センター
小説や物語のなかに出てくるお菓子や豪華なメニューにときめくように、映画ならなおさら!ビジュアル付きで「食」のシーンやセリフに心奪われますね。この本は副題に「映画に出てくる料理を作る本」とある通り、54作品の国内外の映画紹介とともに、魅力的な食べ物や飲み物のレシピも数多く付いています。
たとえばダスティン・ホフマン主演の『クレイマー・クレイマー』(1979)ではダスティン・ホフマン演じる父と幼い息子ビリーがつくるフレンチトーストに注目しています。映画では、妻に家出され、それまで家事や育児に協力的でなかった父が息子にせがまれて滅茶苦茶の手振りでフレンチトーストをつくるシーンが冒頭近くにあり、やがて終盤、父と息子の別れが近づいた頃に再び朝食のために手慣れた様子でフレンチトーストをつくるという名シーンへとつながります。言葉よりも雄弁に語りかけるフレンチトーストはこの映画のなかの重要なモチーフになっていて、キッチンに腰掛けて父のフレンチトーストが出来上がるのを待つ息子のけなげな姿は忘れられません。
もう一つ紹介したいのはデンマーク映画の『バベットの晩餐会』(1987)。家政婦バベットが繰り出す手の込んだ料理の数々が、清貧に暮らす村の人々の心をじわじわととりこにしていく場面は息をのむほど。元々はパリの名店のシェフだったバベットが偶然当たった祖国フランスの宝くじの賞金をすべて注ぎ込み食材を購入。その力量を余すところなく発揮して作り出す味わいが、頑なで心を閉ざしがちな村人の舌と口、胃袋、やがて心まで溶かしていくのです。もちろん見ている私たちも、脳がおいしいものを味わう喜びに満ち溢れてきます。ああ。
さて、めくるめく料理のうち、超豪華なブリニス(小麦粉とそば粉を混ぜて焼いた小さなパンケーキ)を、本では庶民的にアレンジしたレシピにして紹介しています。フェルメールの絵画のように静謐で厳かな雰囲気もこの映画の魅力で、食欲とアートの秋にもぴったりです(アマゾンプライムに加入している方は、今、無料で視聴できますよ!)あれ、映画紹介みたいになってしまいました(笑)。
ちなみに『バベットの晩餐会』については、原作者アイザック・ディネーセンの本もぜひ。映画公開当時に出版された本は岸田今日子さん訳。映画解説もありファン必携の書です!★アイザック・ディネーセン『バベットの晩餐会』(1989)シネセゾン
写真はミール1階の打ち合わせスペースにて。ミールは所長をはじめ、みんな紅茶党!
(スタッフN&C)

皆さま、こんにちは。オリンピックでは日々熱戦が続いていますね。メダルの色はもちろん、選手の頑張りも、目に眩しい夏です。
今日はミール風ブックトーク「読んでミール?」の第11回をお届けします。五感につながる「一文字」テーマシリーズ!前回の「音」につづき、「色」をお届けします。今回も、ブックトーカーふたりのこころの本棚から3冊ずつ、ご紹介します。
第11回「読んでミール?」の始まり、はじまり。
Book Talker Naomi***
①レオ・レオニ 著
『あおくんときいろちゃん』(1959)
至光社ブッククラブ国際版絵本
古典とも言われるこの絵本はレオ・レオニが孫たちにお話をせがまれた時に生まれた作品です。
単純な絵が小さい子供にも分かりやすく、あおときいろが合わさりみどりになるという内容は融合という深い意味で大人にも考えさせられる作品だと思います。
今回の「色」というお題で本を探した時に、同じレオ・レオニの作品でカメレオンが自分らしさを探す「じぶんだけのいろ」と迷ったのですが、単純な絵の中にも色々な感情を表現している「あおくんときいろちゃん」はやはり名作だと思いこちらを選びました。
[参考]レオ・レオニ著
「じぶんだけのいろ」(1975)好学社
②砥上裕將(とがみひろまさ) 著
『線は、僕を描く』(2019)講談社
☆第59回メフィスト賞受賞作
この作品は「水墨画」という墨の線だけで描く芸術が題材になっています。いわば黒だけの世界の作品ですが、本書をあえて選んだのは黒一色といいながら、その濃淡やさまざま技法を使って描き出す絵の奥の深さ、そしてその絵の中に色を感じ、魂を感じる内容に心惹かれたからです。
実際に私が水墨画を見てもそれを感じる事が出来るかと言えば難しいかもしれませんが、ただそういう世界があると言う事を知るきっかけとなり、今度じっくりと水墨画を見に行きたいと思いました。
③ブレイディみかこ 著
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(2019)新潮社
☆本屋大賞2019ノンフィクション本大賞受賞作
☆第73回毎日出版文化賞特別賞受賞
☆第7回ブクログ大賞(エッセイ・ノンフィクション部門)
これは英国に住むアイルランド人の父と日本人の母を持つ少年の中学校生活を、母であるブレイディみかこさんの目線を通して書かれた作品です。
題名にあるホワイトとイエローは肌の色をさしています。
肌の色については差別問題がはらんでいて、有名なところでは絶版と復刊を繰り返した「ちびくろサンボ」という絵本があり、また差別用語に繋がるということでクレヨンの「肌色」は2005年には完全に無くなり「薄橙」又は「ペールオレンジ」と呼ばれるようになりました。
肌の色や国籍、貧富の差などの色々な問題を、時に迷いながらも自分の力で解決していく息子の姿に「子供ってすごいな!」と思わされます。
親というのは心配のあまり、とかく子供に干渉したり指示を与えたりしがちですが、ブレイディみかこさんの一緒に考え悩み、最終的には子供が決めた事を認めて応援するというスタンスがとても良いと思います。
子供の持つ無限の可能性と、親としての在り方を教えてくれる作品のような気がしました。
題名の「ブルー」は日本でも正式な英語の意味でも使われる「気持ちがふさぎ込んでいる」「憂鬱」をさしているかと思いますが、最後のページで息子が、今は「ブルー」ではなく「ぼくはイエローでホワイトでときどきグリーン」と言っている言葉がとても印象的でした。
ちなみにこの「グリーン」という英語の意味には「環境問題」とか「未熟」「経験が足りない」などの意味があるそうです。
今は「グリーン」という彼がこれからどんな色に変わっていくか…いち読者としてもとても楽しみです。
Book Talker Chie***
1 堀川恵子 著
『教誨師』(2014)講談社
☆第一回城山三郎賞受賞
教誨師(きょうかいし)という言葉をご存じでしょうか。広辞苑には「教誨」の意味として(1)教えさとすこと。(2)刑務所で受刑者に対して行う徳性の育成を目的とする教育活動。宗教教誨に限らない。「――師」とあります。
本書の“教誨師”は、拘置所で死刑囚と唯一面談できる民間人として、無報酬で死刑囚と向き合う宗教者であり、その苦悩や葛藤を描いています。死刑囚と対話し、死刑囚からの問に答え、さらに刑の執行にも立ち会うという想像を絶する困難な役割を半世紀もの間続けた広島出身の浄土真宗の僧侶、渡邉普相の告白を中心に、ノンフィクション作家として名高い堀川恵子によって本書はまとめられました。
読み進めるのは恐ろしいけれども、読まなくてはいけないと駆り立てられるのは執筆者の筆力と、やはり教誨師である渡邉普相の人間力に惹かれるからだろうと思います。渡邉の没後に出版する、という渡邉との約束通り、この世に送り出されました。
「色」というテーマで思いを巡らせたときに、この本には色を感じる描写がほとんどないことに気づきました。死刑囚と語り合う拘置所の教誨室や、死刑執行の場が無彩色の世界観だからでしょうか。渡邉が時折、死刑囚たちに差し入れる靴下には、明るい気持ちになれるようにと派手な色を選ぶこともあるものの、その色が何かのアクセントになっているとは感じられません。彩りの極端な少なさが、生きるとは死ぬとはという根源的な問を鮮明にしているようにも思えるほどです。
そんななかで、まさに一瞬、色彩が走馬灯のようにイキイキと流れ出すのは、拘置所から刑場へと移送されるバスの車窓です。すこし本文を引きます。「格子越しに窓の外を見つめる山本(注:死刑囚)にも、言葉はなかった。車窓には、死刑囚に対しても、いささかの分けへだてなく穏やかな日常生活が広がっている。身体からはみだしそうな大きな赤いランドセルを背負った子どもたち、その傍らで花壇に水をやる主婦の姿、信号が変わる度、目の前をどっと横切るサラリーマンの一群。山本は、今生最後の風景をじっと目に焼き付けているようだった」。
娑婆の世界の色味をどれほど愛おしく感じただろうと思う場面です。重い内容の本ですが、いつか読んでみてください。
2 安房直子 著
『きつねの窓』『夕日の国』〜安房直子コレクションより〜
(2004)偕成社
安房直子さんは、50歳という若さでこの世を去った童話作家。幻想的で短いお話が多く、そのなかには色や香りが大切なモチーフとしてよく出てきます。
『きつねの窓』はある日、桔梗の花畑に迷い込んだ少年のお話で、彼はそこで出会ったきつねに、桔梗の花の汁で両手の親指と人差し指を青く染めてもらいます。その青く染まった4本の指をつかって菱形に窓をつくってのぞくと、会えないはずの人や光景が見えるのです。亡くなった妹や焼けてしまった家の様子に、指の窓さえ通せばまた会える。そんな喜びもつかのま、うっかりいつもの習慣で手を洗ってしまう・・。
コロナ禍のいま、うっかりではなく、すっかり手洗いが身についた私たち。でも、もしも桔梗の汁で染めた指があったなら、洗い流したとしても、温かな感触や記憶はそっと残るといいなあと思います。
『夕日の国』は、なわとびの紐にオレンジ色の液体をたらしてから飛ぶと、オレンジ色の風景が見えてきて、夕日の国へ行けるというお話です。安房直子さんのお話はあの世とこの世の境を行き来する時空旅行のようでもあり、どこか寂しさも漂うのですが、摩訶不思議な世界を素直に受け止めて、心にさーっと風を通してみたいような時には、さまざまな色がそっとその世界へ連れて行ってくれます。
もう一つ。私が一番好きなお話は『ハンカチの上の花畑』。ここでは小人にあげる小さなビーズの金色と、ハンカチの隅にある小さな刺繍のブルーが、ふたつの世界をつなぐ色として登場します。
ちなみに安房作品の紹介は「読んでミール」で2回目となりました(笑)。どうしても幼い時から好きな作家作品から離れられない私です。今回は、色のやさしさだけでなく、輝きや透明感が、安房作品の魅力を引き立てているような作品を挙げてみました。
3 山根京子著
『わさびの日本史』(2020)文一総合出版
☆第12回辻静雄食文化賞受賞
わさびが日本固有種で、日本に栽培起源があることを明らかにした研究者であり、自称「わさび応援隊長」の山根京子さん(岐阜大学准教授)による、まさにわさびづくしの一冊。栽培植物起源学という学問の道を行く山根先生は、「わさび」をテーマに、これまでに中国の奥地や日本全国300か所以上に現地調査されています。ちなみに栽培植物起源学とは山根先生の場合、現地調査、詳細なDNA分析、さらに文献や資料の研究によって、植物が野生植物から栽培植物になった場や時代、どんな民族によってなしえたかということを明らかにするのが目的。
さて、どこをとっても興味深い本書ですが、深いところは新聞各紙の書評を参考にしていただくとして、今回は「色」に注目してみましょう。わさびをイメージする色がキーカラーとなり、カバーや見返し、目次ページを彩っているのが印象的で、この色合いがわさびの世界へと入っていく扉です。そして中身に入っていくと、植物好きで歴史好き?の人にはワクワクしてくる章立てで、謎解きのような展開。巻末の歴史年表も面白く、読者も知らぬ間に、わさび愛に満ちていくという次第。わさびの魅力は香りやツンとした刺激を伴う味わい、そして清々しい色もその一つ。キーカラーが本書の濃い中身を引き立てるというのは、まさにわさびの本分ではないでしょうか!
ところで、デザイナーや印刷業の仕事に欠かせないアイテムとして、色見本というものがあります。DIC(旧社名・大日本インキ化学)の色見本「日本の伝統色」を見てみると、「山葵色(わさびいろ)DIC-N849」がちゃんとありました!私の手元にある古い色見本にはこんなコメントが添えられています。「山葵は清流にしか育たない。その根を食用に供するが、この色名が実際の色よりも青味にイメージされるのは、その育つ清らかな環境のせいか、またはその味の爽やかな辛みのせいかもしれない」。
なるほど!たしかに色見本の山葵色は青っぽいのです・・・。ちなみに『わさびの日本史』のカバー等に使われているわさび色は、この色見本で探すと「豌豆緑(えんどうみどり)DIC-N836」に近い・・・、でも、わさびを連想するのには絶妙な色味なんですよ(笑)。
(スタッフN & C)
写真はDICの色見本「日本の伝統色」。見本も本と考えると、面白い発見の宝庫です!

皆さま、こんにちは。
今日はミール風ブックトーク「読んでミール?」の第9弾をお届けします。
テーマは「冬」。本当は雪の舞う時期にお届けしたかったのですが、三寒四温の時期になりました。せめて、本格的な春になる前に!とお贈りします。
今回もブックトーカーふたりのこころの本棚から3冊ずつ、ご紹介します。
第9弾「読んでミール?」の始まり、はじまり。
Book Talker Naomi***
① 角幡唯介 著
「極夜行」(2018)文藝春秋
「極夜」とは「日中でも薄明か太陽が沈んだ状態が続く現象のことをいい、厳密には太陽の光が当たる限界緯度である66.6度を超える南極圏や北極圏で起こる現象(対義語は白夜)」です。
著者である探検家の角幡唯介は「極夜の世界に行けば真の闇を経験し本物の太陽を見られるのではないか」との思いで、氷点下30度台のグリーンランド北西部へのひとり旅に出ます。それは氷河を渡り氷床やツンドラ地帯を進む過酷な旅で、生死を分ける危険が常につきまとう探検です。
でもこの旅には力強い相棒がいました。40㎏近い大きな犬、ウヤミリックです。白熊対策や橇(そり)を引いてもらう力になるだけではなく、何よりも精神的な支えになり、太陽の出ない闇の中にずっといると鬱状態になる「極夜病」から救ってもくれました。
氷河が割れそうになったりブリザードにあったりと色々な危険に遭いましたが、最大のヤマ場は前もって準備していた2か所の食料等のデポ(保管場所)の1つが白熊に荒らされるというアクシデントがあった時でした。それが有ればあと2か月は休養をとりながら太陽が出る瞬間を見る事が出来るはずでした。
そこで彼はとりあえず獲物を捕まえて食料確保をしながら、何とかそこに残る努力をしてみようという選択をします。
食料が少なくなっていく中でどんどん痩せていく相棒のウヤミリック。その姿を見て自分の残り少ない食料を分け与えようかと思い、ウヤミリックが死んだらその肉を食べ自分はあと何日生きながらえる事が出来るかを考える。そんな極限状態の中で待っていたものは……。
やはり作り物ではなく実体験したものは胸に迫ってきます。私は何度も泣いてしまいました。
皆さんもこの本を読む事で究極の冬を体験してみませんか?
② 三浦綾子 著
「氷点」(1965)朝日新聞社、角川文庫
これは院長夫人が若い医師との逢い引きの最中に3歳の娘を通り魔に殺され、そんな妻への復讐の為に、その殺人犯の娘を養女にするという襲撃的な始まりをする余りにも有名な小説です。
丁度この本を読んだ思春期の頃、著者の三浦綾子さんと同じ北海道の旭川市に住んでいて、この養女、美しく頭も良く純粋な陽子に憧れを抱いていました。
でも半世紀を経て今の年齢になると、陽子という娘は真っ直ぐ過ぎて生きづらいだろうなと思うようになりました。
「氷点」では、実際にそういうラストを迎えますが、続編の「続氷点」で、本当の殺人犯の娘との関わりの中で成長し、陽子の心に出来た氷点は少しずつ溶けてきたのではないかと思います。
それにしても犯罪者の家族というだけで肩身の狭い思いをするのはいつの時代も同じですね。今は更にコロナに感染しただけでバッシングをうけたりもします。心の氷点が消えるような世の中になってほしいですね。
[参考]「続氷点」(1971)角川文庫
③ 小泉八雲 著
「雪女」(1904)偕成社、講談社、恒文社 他
日本人なら誰もが知っているこの物語はギリシャ生まれのイギリス人(後に日本に帰化)パトリック・ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が「怪談」にまとめたものです。
この作品は、私が十数年続けている朗読の発表会で2年前に扱ったもので、その時に雪女(及び雪)を私自身が演じて感じたのは、氷の様に冷たいはずの雪女は、実はとても熱い心を持っているということです。
巳之吉を好きになり、雪女の世界のタブーをおかして人間と結婚し子供を10人も作る。しかし巳之吉がうっかり雪女の事を話してしまい人間界に居られなくなった時も巳之吉を殺さず子供達を託して去っていく。
表面上は冷たく怖いイメージですが、実は愛情深く燃える様な熱い心を持っているのではないかと思います。
よく知られたお話も別の角度から読んでみるとまた違う世界が見えるのではないでしょうか?
Book Talker Chie***
1 E・ポター著 村岡花子訳
『スウ姉さん』(2014)河出文庫
現代の私たちの暮らしと比べれば、ツッコミどころも満載ながら、自分のこと以上に誰か身近な人のために動き、働き、つねに頼られる主人公のスウ姉さんに、まわりの人物を重ねたり、自身がそうではないかと思ったり。スウ姉さんはどの時代にも、どこの国にも、どんな家族にも居る存在ではないかと、そんなことを思わせてくれる本です。
著者のポターの代表作といえば『少女ポリアンナ』(パレアナとも言われる)で、どんなに大変なことでも「喜びのゲーム」に置き換えて幸せを抱きしめるポジティブシンキングな少女のお話。ポリアンナも村岡花子が昭和初期に訳し日本に紹介したことで知られますが、同じ女性を主人公にしながらも『スウ姉さん』※(昭和7年訳出のタイトルは『姉は闘ふ』)の世界観は、人と人の交差をもっと掘り下げているように感じます。村岡花子はポリアンナ以上にスウ姉さんを紹介したかったのではないかと、世に存在する多くのスウ姉さんたちに光を当てたかったのではないかと思います。
さて、主人公のスウ姉さんはどんな人物なのでしょう。彼女はボストンに住んでいて、時代はおそらく20世紀前半。豊かな暮らしの中にいて、母亡き後、父や妹、弟に頼られっぱなし。恋人も財産家の彼女との結婚を早く早くと急ぐ。でもスウ姉さんには本当は熱望していることがありました。それは才能があるといわれたピアノで多くの人に拍手喝采を浴びるような音楽家になり、家族にとって誇らしいと思えるような存在になること。でも、彼女が羽ばたくことを家族が許しません。家族のことを一番に考えるべき存在や立場としてスウ姉さんを閉じ込めるからです。そのうえ、父の銀行が破綻し一家は財産を失い、父は精神的に幼児になってしまう。妹も弟もそんな父の姿を否定して、介護はすべてスウ姉さんに。しかも、恋人との関係も不鮮明になり、彼女はこれまでしたことのない家事に奮闘し、弟や妹のため一家の稼ぎ手となってピアノを教えるという日々に突入していくのです。
こうしてストーリーをたどってみると案外よくある物語なのかもしれません。でも、家族のためにじゃがいもの皮を剥き続ける、いくら剥いても剥いてもじゃがいもの皮が減らない、といった例えが示すように、普遍的な葛藤が描かれていて、深みがあり、物語の世界に引きつけられます。
苦しむスウ姉さんが何かを乗り越える時に現れるのが、何度も訪れる「冬」という季節のような気がして、この本を挙げました。何度も訪れる冬のあとには何度も春が来て・・・。その息吹が人の気持ちを明るくし思い直し、生き直していく力となるのかもしれません。スウ姉さんは耐えながら弾力を増しながら日々を生きる。そういう物語として大事にしていくのも素敵です!
2 M.B.ゴフスタイン著 末盛千枝子訳
『ピアノ調律師』(2012)現代企画室/復刻版
ピアノつながりで、私の最も好きな絵本をご紹介します。絵本といっても文字が多く、大人の読み物として本棚に置いておきたくなる本。
主人公は両親を亡くしておじいちゃんに引き取られた小さな女の子デビー。おじいちゃんの職業であるピアノ調律師の仕事に並々ならぬ興味を持ち、こころの多くをピアノ調律の作業や道具に奪われています。でもおじいちゃんは孫にはピアノ調律師よりもピアニストになってほしいと願っています。
そういうふたりがあるとき、雪道用のオーバーシューズを履いてコートを着込み、有名なピアニストのコンサート前の調律に向かいます。調律を始めてしばらくすると、おじいちゃんが孫にちょっとお使いを頼みます。そこから始まるお話がとても素敵です。まわりの大人は巻き込まれながらも、大人ならではのやさしさもそっと発揮していきます。この本を手にすると、ココアやシチュウなど湯気のあがるものを思い浮かべるのは物語の季節が冬だから?だけど、心身がほっと温まるだけではない、どこか、大切なものを大切にしつづけることの大切さを訴えるという、強さや厳かさを私は感じるのです。内なる熱と外の冷たさ。冬という季節がこの対比を描き出し、届けたいメッセージを支えているのではないかと想像しています。
3 M.B.ゴフスタイン著 谷川俊太郎訳
『ふたりの雪だるま』(1992)すえもりブックス
ゴフスタインが好きになり、彼女の作品はいくつか私にとって大切な本になりましたが、そのなかのもう一冊を冬にちなんでご紹介します。
この雪だるまの絵本は、絵が中心。言葉はとても少ないのですが、描かれた絵の中からたくさんのこころの動きが伝わってくるようです。ストーリーも素敵ですが、絵のタッチも素朴で暖かく、雪が降ったり積もったりする様子が目に見えるよう。
主人公はお姉ちゃんと弟。ふたりにとって初めての大雪が降った朝、ふたりで庭に出て雪だるまを2つ作ります。作ったのですが、どうやら、お姉ちゃんにとっては作った瞬間から雪だるまは作り物ではなくて、自分たちと同じ生きているもののように感じたのではないでしょうか。
やがて夕暮れ。家族で食事を囲んでいると、ふとお姉ちゃんは思うのです。雪だるま、どうしているかなあと。そういう誰もが経験したような気持ちの揺れや動きを、父や母が受け止めて小さな物語がつづきます。幼い弟くんの喜びもいい味わい。こんな愛しい日々に、子も親も、雪だるまも幸せを感じていてほしいと思います。
写真は近所の梅林公園で散歩した時のもの。やがて小さな春が見えてくるはず・・・

(スタッフN&C)
新着記事
カテゴリー
アーカイブ