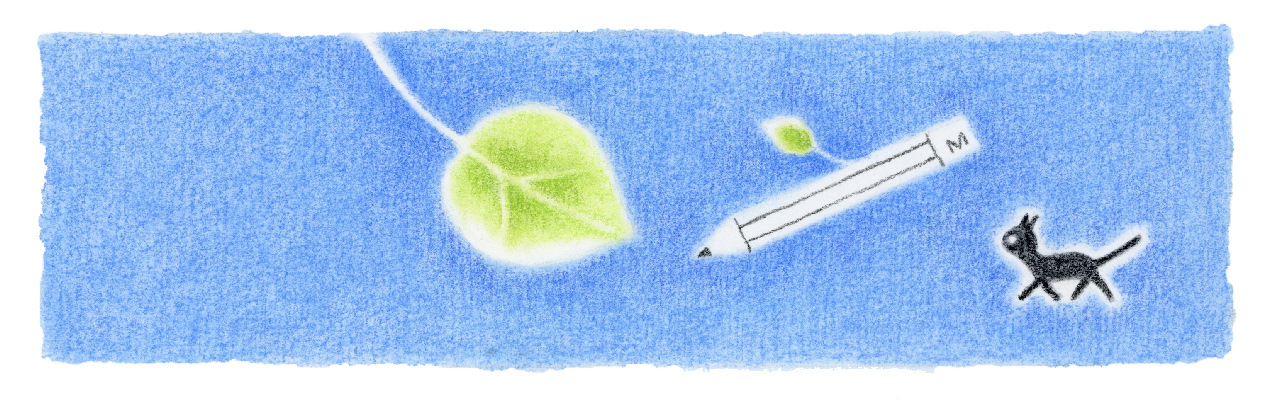
皆さま、こんにちは。ブログの更新の「間」があいてしまいました。コロナ禍からなかなか抜け出せない日々ですが、会えない時間も「愛」を育てられますように!!
さて、今日はミール風ブックトーク「読んでミール?」の記念すべき第10回をお届けします。「春・夏・秋・冬」をテーマにしたブックトークを終え、次なるテーマをどうしよう?どうする?と考えまして、「音・色・香・味・触れる」に決めました。そう五感がテーマです!
今回は「音」をテーマに、ブックトーカーふたりのこころの本棚から3冊ずつ、ご紹介します。
第10回「読んでミール?」の始まり、はじまり。
Book Talker Naomi***
①恩田 陸 著
『蜜蜂と遠雷』(2016)幻冬舎
「音」というテーマを考えた時に1番初めに思い浮かんだのがこの作品でした。
この本を読んだ時、確かにピアノの音が聞こえたような気がしました。
何故だろうと検証してみますと、ピアノを弾くシーンの時、そのイメージを想像しやすい情景を文章で表現しているような気がしました。
確かに映画やドラマで使われた曲は、その曲を聞くだけで、その映像が浮かんできます。…ということは映像が鮮明に浮かぶと、曲が聞こえる(ような気がする)のかもしれません。言葉と音、そして映像。不思議なつながりですね。
この作品は有名ピアノコンクールに出場した4人の男女のお話です。
第1、第2、第3審査と進むと、最後の本選はオーケストラとの共演になります。
各審査は、それぞれに指定された中から自分で選んだ曲で構成していきますが、第2審査ではこのコンクールの為に作られた課題曲「春と修羅」があり、その後半に自分の自由な発想で弾く部分があって、作曲の力も試されます。
出場者が少しずつ落とされ、ピアノ演奏の精査がなされていく中で、各自の色々な思いが交差して、一緒にハラハラドキドキしながらラストまで一気に読んでしまいます。
なおこの作品は2019年に映画化され、その中では(想像では無い)本物の凄いピアノが聞けます。特に課題曲「春と修羅」は同じ曲とは思えないほどの各自のオリジナリティが出ています。(それぞれの役に合った有名ピアニストが影武者です)
またスピンオフ的作品「祝祭と予感」は2019年に出版され、知りたかった過去の話やその後のエピソードが明らかにされますので、合わせて読むと更に一層楽しめると思います。
(参考)「祝祭と予感」(2019)幻冬舎
② 宮下 奈都 著
『羊と鋼の森』(2015)文藝春秋
これは高校生の時に偶然見たピアノの調律に魅せられて、何のバックグラウンドも無いまま調律師を目指した少年の成長物語です。
ピアノというのは、森から切り出された木の枠の中で羊の毛で作られたハンマーが鋼の弦を叩いて音が出ます。それを調律師が色々な技を使って音階に作りあげます。
その基準音となる「ラ」の音は時代と共に変化して、モーツァルトの頃は422ヘルツだったのが戦前には435ヘルツ、そして今は440ヘルツが世界共通になりました。(因みに440ヘルツは赤ん坊の産声の高さです)
時代と共に少しずつ高くなるのは明るい音を必要として、求めるようになったからでしょうか。
そして調律師は弾く人の好みによって、音を高く響かせる事も、軽やかにする事も、重厚な音にする事も出来、ピアノコンクールでは必ず調律師が側にいて、ひとりひとりに合わせ、その都度調整している事は『蜜蜂と遠雷』でも出てきました。
ただ人の感性は色々で求める音を知るのは至難の業。迷う少年に、彼が調律師を目指すきっかけとなった師は「自分の理想とする音は小説家の原民喜(はらたみき)の文章の中にある」と語ってくれました。
「明るく静かに澄んで懐かしい文体、少し甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体」
理想の音を求めまだまだ修行が続く少年を心から応援したいと思います。
③ 町田 そのこ 著
『52ヘルツのクジラたち』(2020)
中央公論新社
クジラは10〜39ヘルツで鳴くが、他のクジラが聞き取れない高い周波数で鳴くという世界で一頭だけのクジラが確認されています。たくさんの仲間がいるはずなのに、何も届かない。何も届けられない。そのため世界で一番孤独だと言われているクジラです。
聞き取れない52ヘルツの声を上げていた自分の声を聞き、救い出してくれた人…その大切な人の声に気付く事が出来ずに死なせてしまった事実に傷ついていた女性は、自分と同じように52ヘルツの声を上げている少年を助けようと動き始める。
この作品の中には虐待や育児放棄、そしてジェンダーやモラハラなど数々の問題が含まれています。
主人公は自分の辛い経験から少年の52ヘルツの声を聞くことが出来たのですが、このお話の中にはそういう経験が無くても一生懸命聞こうとし助けようと努力をする沢山の人達も描かれています。
52ヘルツの声は容易には聞こえないかもしれませんが…常に聞こうと努力する人でありたいと思います。
本作は「2021年本屋大賞」受賞作です。
Book Talker Chie***
1 小泉文夫 著
『小泉文夫フィールドワーク 人はなぜ歌をうたうか』(1984)
「音」というテーマで思いを巡らせたときに思いついたのがこの本です。今から40年近く前の高校から大学生にかけての頃に小泉文夫さんという民族音楽研究者の存在を知りました。クラシックやジャズ、ロック、演歌といったジャンルの普段よく耳にする音楽からは離れて、もっと民族的といいますか土着的な音楽があるのだと先生の本をきっかけに気づいたわけです。それは音楽というよりも、音とかリズムといった原始的で根源的なものへの興味をゆっくりと掘り起こす旅をするかのような面白さで・・・印象深いのは、たとえばエスキモーの人たちのなかでもカリブーではなくクジラを食べる地域のエスキモーたちはリズム感が良いというエピソード。カリブーは一人でも狩りができるけれども、クジラは巨大で一人ではとても獲ることができず、しかもクジラを獲るチャンスは年に二回しかないという。つまりチームワークを整えなければ、村全体の半年分の食料や生活物資をまかなえないのです。そこで大勢で声を合わせ、リズムを合わせる練習をした。それが歌や太鼓だったという話です。これは生きるために拍子を揃えるという例の一つですが、ご存じのように太鼓の音は、伝達という意味からも生きていくのに重要な要素です。
小泉先生の興味の広がりはとめどなく、世界を駆け巡られました。現地へ行き、現地の人の歌や音を集め(録音して)、歴史を探り、「なぜ?」と考察する。その果てしないフィールドワークを文章に書き起こしてくださった労力は、56歳という若さで亡くなった先生の、まさに命を削っての作業だったのではとも思うのですが、きっと小泉先生ご自身は、この驚きや感動を独り占めしてはならぬと突き動かされてお書きになったのではと思います。世界や人類は多様であるということを「音」を通じて実感されたことが原動力であったのではないでしょうか。
昔、兼高かおるさんという女性が世界を飛び回る旅のテレビ番組がありました。インターネットもない時代に、ありとあらゆる世界の風景や人々、暮らしの音も届けてくれました。小泉先生の本も世界の多様を届ける貴重な記録であり道標であり続けると思います。
小泉文夫先生の著作としては『音のなかの文化』『呼吸する民族音楽』(ともに1983、青土社)もおすすめします!
2 村上春樹 著
『遠い太鼓』(1990)講談社
村上ファンのなかには、長編好き、短編好き、エッセイ好き、全部好きといろいろなタイプがいらっしゃると思います。私の場合はたぶん全部好きに入ると思いますが(笑)、「音」というテーマに照らし合わせたときに思い浮かんだのがこのタイトル名を持つエッセイ集です。『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』を執筆した頃、彼は日本では暮らしていませんでした。イタリアやギリシアなどヨーロッパにいたのです。その頃に綴った旅行記であり滞在記は、海外旅行に行けない今、異国の空気を感じるのにも良い本です。
今あらためて読み返すと、村上さんが日本を離れて執筆をしようと思った40歳の頃、精神的にクリアになれるところに身を置きたかったのではと感じます。頭のなかに蜂を飼っているらしく(それはおそらく耳鳴りのことと思います)、蜂のぶんぶん音も含め、さまざまな雑音にさいなまれる日々から解放されたかったのではと。村上さんのような人気作家でなくとも、いつもの音、絶え間なく続く音から逃れたい時はあります。音とは風景であり、環境であり、内的な思いの重なりから生まれる何かかもしれません。うるさく感じて離れたいと思うけれども常にともにある。そして、ある時、ふっと別の音にもひかれる。
この本はこのように始まります。
ある朝目が覚めて、ふと耳を澄ませると、何処か遠くから太鼓の音が聞こえてきた。その音を聞いているうちに、僕はどうしても長い旅に出たくなったのだ。
タイトルの「遠い太鼓」はトルコの古謡からとったものとか。音に誘われて旅に出る。それも人間らしい素朴な行いなのかもしれません。音の原始は、あるいは、音を求める原始は、生きているものがすべて持つ、脈動なのではと、私は勝手に想像しているのですが・・・。
3 ウィリアム・ブレイク作 池澤春菜・池澤夏樹 訳
『無垢の歌』(2021)毎日新聞出版
ウィリアム・ブレイク(1757〜1827)は産業革命期のロンドンに生きた詩人で画家、銅版画職人。自らの詩と彩色版画による幻想的な詩集をつくりました。また預言詩『ミルトン』に収められた詩「エルサレム」はイギリスの国家として歌われています。ブレイクの詩はさまざまな分野の作家に影響を与え、日本では柳宗悦、ノーベル賞作家の大江健三郎さんもその一人です。
さて、そのようなブレイクの詩は私には難しいのでは?と長年思っていたのですが、最近手にして感銘を受けたのが池澤春菜・池澤夏樹の訳によるこの本です。親子でもあるふたりがブレイクの詩の訳と解説を分担していて、その言葉がとてもやさしく美しく、調子や音色が素敵なのです。
ブレイクの詩(歌)には音と文字とその両方の美しさがあると、訳者の春菜さんはまえがきで綴っています。「ブレイクの言葉の中にある優しさ、愛おしさ、明るさや清らかさ、善きものに向かう心をこぼさずすくえるように」日本語にしたそうです。
思えば詩(歌)は音から生まれ、文字から生まれています。両者はきっと不可分の存在で、音の聞こえない人、文字の見えない人にも、その両方を届け合うことで、意味や情景、思いとなって膨らみ、詩が伝わるのかもしれないと思います。
池澤親子が訳者となって心をこめて届ける無垢の歌たち。ブレイクの音と文字の両方の良さをこぼさぬように、大切に私たちに渡してくれている気がします。
(スタッフN&C)
どこかから音が聞こえてきそう。風や雲の流れ、物語の言葉のなかに・・・。

新着記事
カテゴリー
アーカイブ