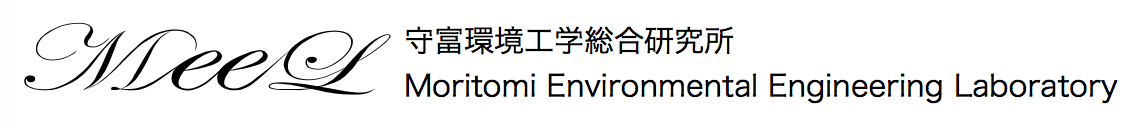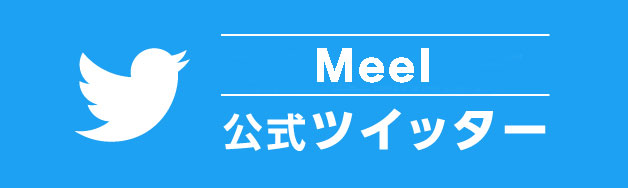2023/11/12
11月となり,新着情報としては9月を中心としたご報告となりすこし古いのですが,以下,所長の守富寛から最近の状況をお伝えいたします。
2023年9月はコロナ禍を含めた3年の中では,久しぶりに面談での出張の多い月でした。
まず9月の第1週(8/28-9/1)は環境省・エックス都市の途上国向け水銀排出抑制の研修であり,コロナ前にも東南アジアの国々(これまでに5カ国ぐらい)を対象に行なっていましたが,今回はフィリピンとネパールの2カ国でした。各国内の水銀の排出流れを日本国内で検討してきたマテリアルフロー検討手法をベースに1週間をかけて数値化する研修でした。ネパールでの水銀排出源で困っているのは仏像製作であり,小型ですが奈良の大仏様同様,水銀アマルガム法による鍍金(金メッキ)であり,水銀使用量と回収量の推算から入り,回収技術まで話が及びました。英語でのやりとりでしたが,2年近く英語も使わないとあるいは年齢かもしれませんが,慣れるのに時間を要しました。
翌週(9/4-9/5)は経産省・カーボンフロンティア機構(JCOAL)による第32回クリーン・コール・デー国際会議のセッションの一つにモデレータ(司会)を頼まれ,参加しました。かつては公害や地球環境を配慮した石炭の有効利用に関わる会議でしたが,石炭は地球温暖化の元凶であるCO2の排出源とみなされ,火力発電所は2050年までに段階的縮小することになり,石炭などのストック型炭素資源を水蒸気改質して出てきたCO2を回収,水素を燃料とするブルー水素,フロー型のバイオマスなどの再生可能エネルギーにより水の電気分解からのグリーン水素についての技術と将来像について議論されました。1973年のオイルショックから50年の間の石油から石炭へシフトと安定供給,1992年の第1回気象変動枠組条約(COP1)から30年の間,石炭の高効率発電技術の推進に精力を傾けてきた私には,原子力ダメ,石炭ダメ政策には違和感を覚えます。日本ではこの30年間だけでもあまり進まなかったフロー型エネルギーが,残り20年でストック型エネルギーに置き換わるとは革命的な大事業でもなければありえないようにも思われてならないのです。
第3週(9/15)は環境省・JCOALの固体型吸着剤によるCO2回収の委員会において米国(ワイオミング州)で行なっている実証試験の準備状況報告を受けました。液体型吸収剤によるCO2回収実証試験は大牟田で別途行われており,薬剤の安全性の議論をしています。
第4週(9/18と9/20)は中国の電力会社研修として炭素繊維利用と廃棄(風力発電用と思われる)と応用物理学会プラズマ科学部門から炭素繊維リサイクル過程でのプラズマ利用の可能性に関する講演を頼まれました。コロナ禍の2年間は守富研究所内の実験室に籠って「切断炭素繊維を繋ぐリサイクル技術」の確立を目指して奮闘しているのですが,ここでは「リサイクル炭素繊維の回収技術と利活用」の一般的な話をしました。リサイクル炭素繊維の需要供給にはコロナ2年で栄枯盛衰があり,短く切ったチョップド短繊維によるペレット需要は飛躍する一方,長繊維のシート状ペーパーや不織布は水面下に入り,企業間提携で動いているため,情報が得られにくくなっているように思います。講演会で感想を訊ねると「もうそこまで進んでいるのか!」との意見と,「リサイクル材の利用は難しいよね!」の意見をよく耳にします。化石燃料に端を発したアクリロニトリルを2000-3000ºCで熱処理した炭素繊維はエネルギー多消費型の材料であり,「リサイクルは難しくてもリサイクルしないと将来はない」のです。守富研究所の利用幅を拡げる「リサイクル炭素繊維の連続糸化」の技術開発にご期待ください。
国の研究所や大学に籍を置いた時代ならともかく,70代に入った我が身で忙しく新幹線で移動する日々が続くことはもうないと思っていましたが「コロナ明け」が宣言されたようで,移動先や宿泊先で白髪になった方々とマスクなしで語り飲むことで少し若返ったような気がします。
(守富 寛)
参考資料
・水銀マテリアルフロー:https://www.env.go.jp/content/900414997.pdf
・第32回クリーン・コール・デー国際会議:https://www.jcoal-ccd2023.com/ccd/
・米国ワイオミング州でのCO2分離回収技術実証試験設備:https://www.jcoal.or.jp/news/2023/1011.html
・CO2分離・回収技術の概要:https://www.nedo.go.jp/content/100932834.pdf
・第84回応用物理学会:https://meeting.jsap.or.jp/jsapm/wp-content/uploads/sites/16/2023/06/T11.pdf